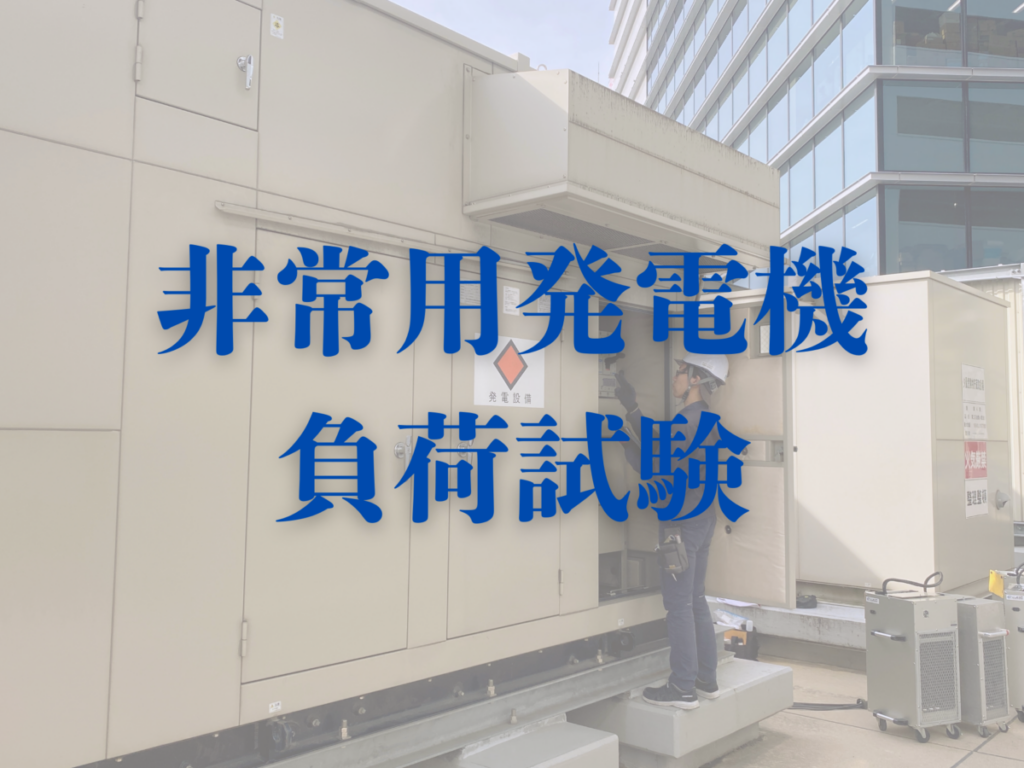
消防法では、非常用発電機の負荷試験の実施が義務付けられている。
非常 用発電機は、災害や停電時に確実に作動することが求められる設備なので、適切なメンテナンスが必要とされています。本記事では、消防法に基づく負荷試験の法的要件、擬似負荷試験の優位性、免除条件について詳しく解説します。
もくじ
1. 消防法における負荷試験
1.1 負荷試験の目的
負荷試験は、非常用発電機が実際の負荷をかけた状態で適切に機能するかを確認するために実施されます。
- エンジン・発電機の動作確認
- 擬似負荷状態での出力性能の検証
- 燃料供給・冷却系統の正常動作の確認
1.2 消防法による負荷試験の義務
消防法第17条および関連法令では、一定規模以上の建築物に設置された非常用発電機に対し、1年に1回の負荷試験の実施が義務付けられています。
また、消防庁告示第12号(平成30年6月消防予第373号)で定められた負荷運転とは以下の通りです。
- 1年に1回、擬似負荷装置、実負荷等にて定格回路回転速度及び出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認すること
- 負荷運転に代えて内部観察等による点検が可能であること
- 上記1、2を実施後「運転性能の維持にかかる予防的な保全策」が講じられた場合、1か2の点検を6年に1回実施すればよいこと
- 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備は無負荷でも未燃焼燃料が残らないため負荷運転は不要であること
2. 擬似負荷試験のと擬似負荷試験
2.1 実負荷試験とは
実負荷試験とは、非常用発電機を実際に稼働させ、消防用設備(スプリンクラーや消火ポンプなど)や施設の設備と連動させた状態で動作を確認する試験です。この試験では、建物内の消防設備等を運転しながら、非常用発電機が適切に機能するかをチェックします。
しかし、試験中には設備内で一時的な停電や瞬間的な停電(瞬停)が発生することがあります。また、エレベーターやポンプなどの設備では、試験の条件である定格出力の30%以上の負荷をかけ続けるのが難しい場合があります。
実負荷試験のイメージ

2.2 擬似負荷試験のメリット
擬似負荷試験は、専用の負荷試験装置を使用し、実際の電気負荷をかけずに発電機の動作を確認する方法です。実負荷試験と比較して以下のメリットがあります。
- 停電など、建物の運用に影響を与えずに試験が可能
- 安定して30パーセント負荷を維持できるため、試験結果が信頼できる
- エンジン内のカーボンの排出が期待できる
- 短時間で試験が完了し、コストを削減できる
2.3 擬似負荷試験の実施方法
擬似負荷試験では、以下のような手順で試験が行われます。
- 専用負荷試験装置を接続
- 発電機に擬似負荷をかける装置を接続し、発電機の性能を計測。
- 段階的な負荷投入によるエンジン性能の確認
- 10%、20%、30%と段階的に負荷を投入し、発電機の状態を確認する。
- 運転データの取得と分析
- 出力電圧・周波数の変動、冷却系統の動作状況を記録。
実際の擬似負荷試験の様子

3. 負荷試験の免除基準と条件
3.1 負荷試験が免除されるケース
一定の条件を満たす場合、消防法に基づく負荷試験の免除が認められます。
- 負荷運転に代えて内部観察等による点検を実施している
- 負荷試験を実施後、「運転性能の維持にかかる予防的な保全策」が講じられている(5年間)
4. 負荷試験結果の記録と報告義務
消防法では、負荷試験の実施結果を記録し、一定期間保管することが義務付けられています。
4.1 点検記録の作成
擬似負荷試験の結果は、以下の情報を含めて記録する必要があります。
- 試験実施日・担当者
- 負荷率・稼働時間
- 異常の有無・対策内容
報告書一例

4.2 点検報告書の提出義務
消防検査時に、過去の負荷試験の記録を届出をする必要があります。
保管期間:原則3年(3年を経過したものについては、点検結果総括表、点検者一覧表及び経過一覧表を保存するだけでよい)
報告対象:消防署、建物管理者、設備保守会社
5. まとめ
擬似負荷試験は、非常用発電機の性能を確認しながら、機器への負担や環境負荷を最小限に抑える最適な方法です。消防法では、一定の基準に基づいて負荷試験の実施が義務付けられています。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
